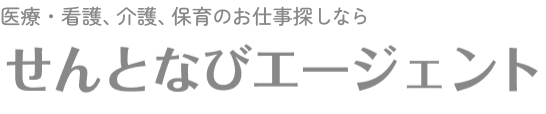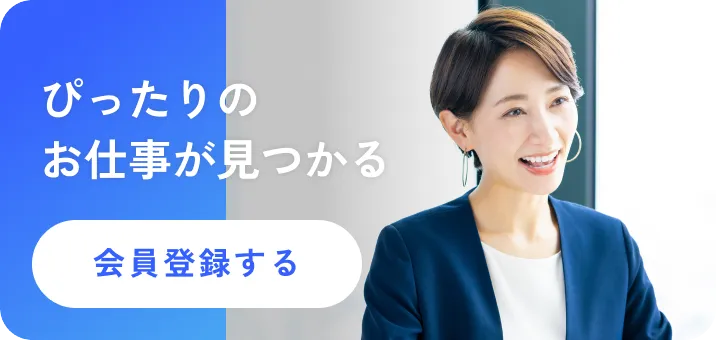障がい者の能力を活かす「業務切り出し」とは?業務切り出しの進め方と事例紹介
障がい者雇用を進めるうえで、「どの業務を任せるか」は多くの企業が直面する課題です。業務切り出しは、本人の能力を活かすとともに、職場の生産性を向上させる重要な取り組みです。本記事では、厚生労働省や自治体が提供する資料・事例に基づき、障がい者の方への業務切り出しの考え方や具体的な進め方についてお伝えします。
採用から入社、業務の切り出しまで障がい者雇用に関するご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせくださいませ。

目次
業務切り出しとは?|目的と意義
業務切り出しとは、既存の業務の中から障がいのある方に適した作業を選び出し、明確に役割を定義して任せる方法です。ただ単に「簡単な仕事を任せる」ものではなく、企業側が業務の再設計を行うことにより、本人の適性に合った仕事を創出する「職域開発」のプロセスです。
- 本人の障がい特性やスキルに合った業務を提供する
- 業務の属人化・非効率を改善し、組織全体の生産性向上を図る
- 職場の理解と支援体制を構築し、定着率を高める

障がい者雇用に関するご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせくださいませ。
業務切り出しの進め方|ステップとチェックポイント
京都府のホームページ「京都府ジョブパーク」では、業務切り出しを以下のようなのステップで整理しています。
■業務改善
業務の選定・支援ツールによる容易化・職場環境の改善・生産性向上活動の継続
■働く方の能力開発
業務遂行とともに成長する・本人意思の確認・レベルに応じた能力開発
参考元:京都府ジョブパーク:職域開発・職務創出支援

企業様や施設様の障がい者雇用に関するご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせくださいませ。
実際の事例に学ぶ|成功企業の工夫と支援活用
実際に障がい者の業務切り出しに成功している企業では、業務の明確化や支援機関との連携を積極的に行っています。
① 事例:製造業における「清掃・検品業務」の切り出し(知的障がい)
ある製造業の企業では、工場内の「清掃」「部品検品」「部材の仕分け」といった軽作業を切り出し、知的障がいのある方を2名配置しました。業務の流れをマニュアル化し、必要な道具の配置を視覚的に整理することで、定着率が向上。現場では「本来の業務に集中できるようになった」と社員の満足度も上がりました。
- 業務の流れを視覚的にマニュアル化 →簡単な説明でも伝わりやすい
- 作業スペースを整理整頓し、移動の負担を軽減 →作業動線の混乱を防ぐ
- 支援員と連携し、習熟ペースを可視化 →個人個人にあった業務内容の設計へ

② 事例:IT企業における「マニュアル作成支援業務」の切り出し(発達障がい)
IT企業では、社内マニュアルのチェック・修正作業を、発達障がいのある方に切り出しました。細かなルールに基づいた作業が得意な特性を活かし、誤字脱字の指摘、図表の整合性確認などを担当。作業ルールを文書化することで他部署との連携も円滑になり、「業務品質の向上にもつながった」との声が寄せられています。
- 業務フローの明確化により混乱を回避 →集中しやすい
- 特性を活かした定型チェック業務を設定 →ルーティン作業や一人で黙々とできる業務の切り出し
- 社内評価制度に反映し、モチベーション向上 →業務の目的やつながりがわかりやすくなる

③ 切り出し案:サービス業での「物品補充・備品管理」業務の切り出し
ホテル業界では、障がいのあるスタッフに対して、「アメニティ補充」「備品チェック」「在庫整理」などの定型業務の切り出しも考えられます。チェックリストと固定スケジュールを用いることで業務の標準化が進み、作業のばらつきも減少。職場全体のサービス品質向上にも貢献できるのではないでしょうか。
- 1日単位で完了する業務設計
- 作業の視覚化・ルーティン化 →固定ルートでの作業指示により混乱回避
- 職場内評価を可視化 →感謝を伝える「ありがとうカード」の使用など
参考元:精神障害者雇用事例集「精神障害者とともに働く」事例8
参考元:日本経営開発協会「障害者雇用実践編」

障がい者雇用に関するご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせくださいませ。
まとめ
障がい者雇用における業務切り出しは、多様な人材活用を実現するだけではなく、職場の課題解決にとっても有効な手段となります。公的資料等の情報収集に加えて、場合によっては人材サービス会社や地域障害者職業センター等での相談も有効となってきます。それぞれの方にあった業務と支援体制を設計していくことが、長期的な雇用安定につながります。
採用から業務の切り出し等、障がい者雇用に関するご相談は、弊社でも承っております。
以下よりお気軽にお問い合わせくださいませ!