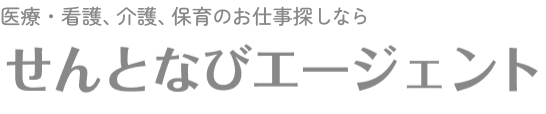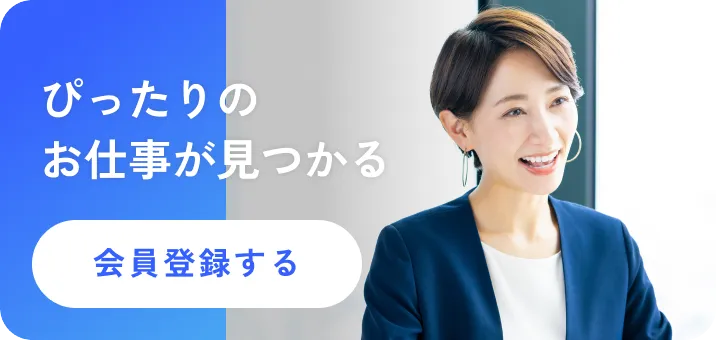就労中も利用できる!支援や障がい者福祉サービスとは?
障がいのある方が就労を目指す際、「働くと福祉サービスが受けられなくなるのでは?」と不安に感じることは少なくありません。実は、働きながらでも利用できる福祉制度や金銭的支援は多く存在します。
本記事では、就労と両立できる障がい者向けの福祉サービスや手当について、わかりやすく解説します。
就労を希望される障がいのある方へ
▶ お問い合わせはこちら
▶ 障がい者雇用求人を探す

目次
働きながらでも福祉サービスは受けられる?
障がいのある方が働いていても、一定の条件を満たせば、さまざまな福祉サービスを受け続けることが可能です。ここでは主な制度を紹介します。
就労移行支援、就労継続支援A/B型、デイケアなど
就労移行支援事業所や、就労継続支援A型/B型事業所
→在職中や働きながらの利用は、原則難しいとされています。
精神科デイケア
→医療サービスとなるため、多くのデイケアは在職中や働きながらの利用も可能となっております。
職場・社会復帰に向けたリワークプログラム(「職場復帰支援プログラム」や「復職支援プログラム」とも呼ばれている)を行っているデイケアもあります。
参照:リワークプログラムとは?種類や対象者、利用の流れやメリットを解説 – 株式会社Kaien – 強みを活かした就労移行支援・自立訓練(生活訓練)
障害年金と就労の両立
障害年金は「生活の基盤を支えるための制度」であり、就労していても受給が可能です。ただし、働く内容や収入、障害の等級によって支給が継続されるか判断されます。
- 障害基礎年金(1・2級):主に国民年金加入者が対象
- 障害厚生年金(1〜3級):厚生年金に加入歴がある方向け
※就労していても「日常生活や就労に支援が必要」と判断されれば継続支給されます
ポイント
- 収入がある=即停止ではない
- 働き方(フルタイムか、短時間か)も考慮される
- 主治医の診断書が大きな判断材料になる
参考元:【日本年金機構】障害年金(受給要件・請求時期・年金額)

各種手当(特別障害者手当など)
以下のような手当は、所得制限はあるものの、就労と両立して支給されるケースもあります。
- 特別障害者手当:日常生活で常時介護を要する方へ支給(20歳以上)
- 障害児福祉手当/特別児童扶養手当:子ども対象の支援制度
- 自立支援医療:医療費の自己負担が軽減される
ポイント
- 所得制限に注意(前年収入が一定額以下など)
- 就労していても受給条件に該当すれば支給継続可
- 手続きは市区町村の窓口へ
参考元:厚生労働省|障害者福祉の手当等

転職や求職を考えている方はこちら
お問い合わせはこちら
障がい者雇用求人を探す
福祉サービスを受けるために必要な手続き
就労しながらも福祉サービスを利用するためには、正しい手続きと継続的な情報提供が欠かせません。
収入による支給への影響
「働いたら年金や手当が打ち切られるのでは」と不安になる方は少なくありません。しかし、実際には急にすべてが止まるわけではなく、段階的な調整が行われることが多いです。
※20歳前傷病の障害基礎年金は所得制限あり
- 年金や手当には「収入の上限」や「支給調整」があり、少しずつ支給額が変動する
- 就労を理由にすぐ停止される制度は少ない
ポイント:
- 事前に収入見込みと制度の関係を確認
- 働き方と制度のバランスを取る
- 就労移行支援などの専門機関に相談を
参考元:日本年金機構|障害年金
.jpg)
障がい者雇用求人をお探しの方はこちら
相談窓口と活用方法
制度をうまく活用するには、専門窓口との連携が鍵です。次のような機関が相談先として利用できます。
- 市区町村の障害福祉課
- ハローワーク(専門援助部門)
- 地域障害者職業センター
- 就労移行支援事業所
ポイント:
- 手当や年金だけでなく、職業相談も可能
- 必要に応じて専門職(ジョブコーチや相談支援員)と連携
- 制度変更に備え、定期的な確認も重要
参考元:JEED|地域障害者職業センター
参考元:せんとなび| 障がい者雇用での就職!相談できる支援機関は?

まとめ
働きながらでも利用できる福祉サービスは数多く存在します。就労の選択肢を広げるためにも、制度の仕組みを正しく理解し、専門機関と連携しながら活用しましょう。
働きながらの支援制度についてもっと知りたい方へ
▶ お問い合わせはこちら
▶ 障がい者向け求人一覧を見る