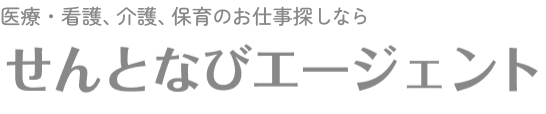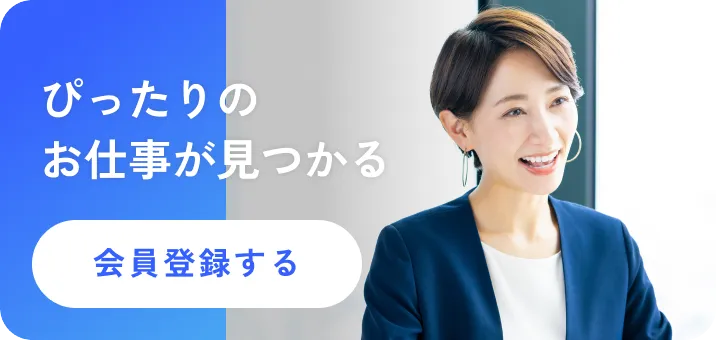「知的障がい」と「発達障がい」の違いとは?サポートのポイントも解説!
障がい者雇用を進める中で、「知的障がい」と「発達障がい」の違いがわかりにくいと感じる企業担当者も多いのではないでしょうか。
それぞれの障がいには異なる特性があり、職場での対応も変わってきます。本記事では、知的障がいと発達障がいの基本的な違いと、企業が理解しておくべき配慮のポイントについて解説します。

▼障がい者雇用をご検討中の企業様へ
▶ お問い合わせフォームはこちら
▶ 障がい者人材紹介サービスの詳細を見る
目次
知的障がいと発達障がいの基本的な違い
定義と診断基準の違い
知的障がいは、概ね18歳未満で発症し、知的機能(IQ70以下程度)と適応行動において明確な困難がある状態を指します。
一方、発達障がいは神経発達の特性に由来し、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障がい(LD)などが含まれます。
→知的障がいが「能力の全体的な発達の遅れ」であるのに対し、発達障がいは「特定の認知・行動の偏り」が見られるのが特徴です。

- 知的障がい:全般的な知的機能の遅れ+日常生活の困難
- 発達障がい:脳の特定の機能に偏りがあり、対人関係や集中力などに特性が見られる
- 重複する場合もある:両方の診断がつくケースも存在
職場で見られる特性と配慮の例
知的障がい・発達障がいの職場での特徴
企業での就労支援において、障がい特性に応じた配慮が重要です。
<知的障がいのある方>
作業が複雑、マニュアル等の内容の理解に時間がかかる等、手順を覚えるのに時間がかかる場合があるため、繰り返しの作業や丁寧な指導が効果的です。また、業務内容やペースに不安感を感じやすい方もいるため、相談しやすい環境を整えていくことも安定的な就業のポイントになってきます。
<発達障がいのある方>
光といった視覚や音などの聴覚などの感覚過敏や、コミュニケーション上苦手な場面があり、業務環境の工夫や具体的な指示が必要になることがあります。

- 知的障がい:マニュアル化、作業の分解、習熟のための反復支援
- 発達障がい:視覚的な手順書、静かな作業環境(ヘットフォン等の使用)、指示の具体化(あれ・それ・適当になどの表現の多用は避ける)
- 共通の支援:定期的な面談、フィードバック、サポーターの配置
参考元:
【障害特性・シーン別対応解説付き】発達障害のある方と一緒に働く上でのポイントとは?(セントスタッフ)
▼障がい者雇用をご検討中の企業様へ
▶ お問い合わせフォームはこちら
企業が理解しておくべき支援の考え方
障がい特性に応じた柔軟な対応を
知的障がいと発達障がいには明確な違いがありますが、いずれも一律に対応できるものではありません。同じ診断名でも特性は個人ごとに異なり、企業には「画一的な枠にはめない支援姿勢」が求められます。
人材紹介会社やハローワーク、支援機関等とも連携した入社前のヒアリング、また入社後の定期的なヒアリングや支援機関との連携を通じて、一人ひとりに合った職場環境づくりが重要です。

- 個別の特性を正しく理解する
- 成長に応じた支援や職務の調整を行う
- 支援者・専門機関と連携して雇用を安定化させる
参考元:
国立障害者リハビリテーションセンター「発達障がいを理解する~みなさんに、わかってほしいこと~」
まとめ
知的障がいと発達障がいの違いを理解することは、職場での円滑な関係構築や定着支援に大きく寄与します。それぞれの特性を尊重しながら、企業として柔軟な対応を行うことが、障がい者雇用の成功につながります。
弊社のような人材紹介会社やハローワーク、支援機関等と連携してみてはいかがでしょうか?
▼障がい者雇用の導入・定着支援をご検討の企業様へ
▶ お問い合わせフォームはこちら